こんにちは。ホームページ管理人の山本です。
夏休みに南アルプスに行ってきました。その時の山行記録です。長文、駄文ですがご勘弁ください。
■日程
2002年7月27日〜8月3日(7泊8日)
■山域 南アルプス
■メンバー 単独
■山行形態 テント縦走。但し、幕営禁止地点、帰りのバスの関係で小屋泊有り。
幕営5日、小屋2泊(素泊り1日、2食付1日)
■コース 広河原〜北岳〜間ノ岳〜塩見岳〜荒川岳〜赤石岳〜聖岳〜椹島
第1日 立川〜甲府〜大樺沢〜二股〜八本歯コル〜北岳山荘(幕営)
第2日 北岳山荘〜北岳(往復)〜間ノ岳〜熊の平小屋(幕営)
第3日 熊の平小屋〜北荒川岳〜塩見岳〜塩見小屋(素泊り
第4日 塩見小屋〜三伏小屋〜小河内岳〜高山裏避難小屋(幕営)
第5日 高山裏避難小屋〜荒川中岳〜荒川東岳(往復)〜荒川小屋(幕営)
第6日 荒川小屋〜小赤石岳〜赤石岳〜百饟洞山の家(1泊2食付泊)
第7日 百饟洞山の家〜兎岳〜聖岳〜聖平小屋(幕営)
第8日 聖平小屋〜聖沢登山口〜椹島〜静岡〜東京〜立川
第1日 7月27日(土) 晴天
大樺沢出合 10:18
北岳山荘 18:30
甲府発9時のバスに乗り、順調に大樺沢出合に到着。スケジュール通り大樺沢出合を出発。天気は上々。大樺沢二俣を過ぎると雪渓が現れる。かなり雪が残っている。途中何回か雪渓上を歩くが荷が重いのと、アイゼンがないため滑りそうになり中止。アイゼンがあればかなり快適に登れたと思う。途中でD沢を分ける。以前高橋と来た時に間違えた沢である。今度は慎重に雪渓を避けながら夏道に取り付く。段々荷が重く肩にのしかかってくる。休み休みの為かなり時間が経ち、後ろから登って来る人が少なくなる。川崎の人と入間の人と3人が抜いたり抜かれたりになり、段々3人がまとまって登るようになる。八本歯のコルまでがきつかった。バットレスに取り付く人達を見ながら、ゆっくり重荷を感じながらハァーハァー登るが足が上がらない。後で気がついたが、完全なシャリバテ様態ではなかったかと思う。暑くて暑くて、沢の水ばかり飲んでいて、何も口に入れずに登っていた。この初日の経験で翌日から休むたびに行動食を口にするようになるが、それでもエネルギー不足を感じる毎日であった。
入間の人と川崎の人とやっとのことで八本歯のコルに到着。入間の人は大樺沢出合に車を置いて日帰り登山を目論んでいた様だが、時間が遅くなり、肩の小屋に泊まることに予定変更。それに付き合うように川崎の人が付いて行った。二人と北岳山荘への分岐で別れ、北岳山荘を見ながら巻き道に入る。到着点が見えると急に元気になり、周りの景色も余裕を持って見られるようになり、花畑の中に珍しい花を発見。写真をとる。ここまではとても花の写真をとる余裕などなかったのだが現金なものである。お花畑の上部に猿が3匹歩いているのを発見。夕方になり、人が少なくなって出てきたようだ。予定より遅れること3時間ほどで北岳山荘のテント場にやっと到着。ちょっと荷物が重すぎたようだ。
テント場の混み具合はほどほど。トイレは村営共同トイレで、特殊な微生物利用の分解型らしい。しかしながら、ちょっと臭いが強いし壊れやすいようで半分くらい使用禁止となっていた。
朝方トイレに立つと、空には満天の星が輝いていた。
第2日 7月28日(日) 晴天
北岳山荘 6:03
北岳 7:03
間ノ岳 11:40
熊の平小屋 14:50
昨日の疲れか朝早く起きられなかった。ゆっくり食事をし、北岳山頂へ向かう。途中で昨日の川崎の人と遭遇。どうしてここに居るのか尋ねると、山頂に着いたには着いたが、夜8時くらいになり入間の人はすでに居なかったとのこと。そこにバットレスクライミングの人達が到着し、肩の小屋へ一人で降りるのは危険だから、我々と北岳山荘へ行こうということになり北岳山荘に泊まったとのこと。入間の人と昨晩連絡を取ろうとしたがとれなかった。心配しているだろうと思い、これから肩の小屋へ行くつもりだとのこと。山頂まで同行し、記念写真を撮り別れる。山頂からの眺めは良く、360度の展望であった。北岳山荘にとって戻り、熊の平小屋へ向かう。昨日は到着が遅かったこともあり、食料はほとんど減っていない。もっと荷を軽くしたかったのだが。
間ノ岳から三峰岳への下って登るのが辛い。三峰から三国平までが非常に長く感じられる。荷が重い。熊の平ではなんとか荷を軽くしなければと考え考え進む。林間のテント場に到着。小屋はその先にあり、小さいがなかなかきれいな小屋である。テント場の脇には水が流れており、不自由しない。隣のグループは名古屋のおじさん4人組。これから聖岳まで行く予定というとオーと驚いていた。自分たちは塩見岳で三伏峠から登るグループと待ち合わせなので、明日はのんびり雪投沢まで行けばよいのでゆっくりとのこと。こちらはとにかく荷を軽くするためソーセージ、缶詰をつまみにビールを飲み、素麺を少し多めに食べる。明け方に雨が降り、雷が鳴った。テントはびしょびしょになり、折角軽くした荷物がまた重くなった。
第3日 7月29日(月) 午前中雨、午後曇り
熊の平小屋 6:08
塩見岳東峰 12:45
塩見小屋 14:30
今朝方の雨でテントが濡れ、荷がまた重くなった。途中で入間からきた73歳のお爺さんと抜きつ抜かれつとなる。お爺さんの話ではここは天国の道というそうである。確かに林の中で、高低さが少なく、気持ちの良い道ではあるが、何しろ雨でカッパを着ているので蒸し暑い。雨はそれほどでもなかったので、カッパは上半身だけで下半身はつけなかったが蒸し暑い。それと何といっても荷が重い。途中何回か抜いては抜かれたが最後は完全に置いていかれた。本日の予定では、塩見小屋を過ぎ三伏小屋まで行く事になっていたが、かなりバテ気味で、塩見小屋で素泊まりとした。小屋は小さいので、完全予約となっているが、今日は客が少なそうなので、丁重にお願いをし、泊めてもらった。小屋の外の仮小屋で8畳に10人とのこと。この時期にしてはまずまずと思う。水場を訪ねると往復30分とのこと。早速出かけるがかなり下る。いい水場で全身を拭いたが、往復約1時間かかった。どうもここら辺の小屋主の言うことは当てにならないと思う。だがなかなかいい水場で生き返った。ここでも荷を軽くするため積極的に食べたが、だんだん食が細くなっていくのを実感した。
ここのトイレは小の方は流すが、大は完全な紙おむつ状のものに入れて集め、下に降ろしている。南アルプスでは出色のトイレだ。夕方北側の山々が夕照の中できれいに望めた。
第4日 7月30日(火) 晴天
塩見小屋 5:00
高山裏避難小屋 16:30
塩見小屋の主人から高山裏の主人宛ての手紙を預かる。飛脚代行である。いつも文通をしているらしいが、なかなか高山裏へ抜ける人が少ないらしい。特に高山裏から塩見に来る人は少ないらしく、文通もままならないらしい。
入間の73歳の達者なお爺さんと三伏小屋への分岐で別れる。ここから先は来年登る予定とか。とにかく元気なお爺さんである。
三伏小屋は沢に面した古い作りの小屋である。テント場は大きい。その大きさで道を間違えた。なんと元の道を歩いていたのだ。お爺さんと別れた分岐でやっと気がつく始末。往復40分近い損失。ダメージが大きい。三伏小屋に戻り道を探すも道標は一切なし。地図で確認、方向を決めて歩き出す。さっきの失敗が頭に焼きつき足取りが重い。途中でやっと三伏峠←→小河内岳の標識を見つける。「山岳」Vol.96(2001年号)に再録された紀行文(「山岳」第1年第3号に掲載の明治39年に行われた荻野音松氏の「駿州田代山奥横断記」に書かれた「間ノ岳(明治時代の塩見岳呼称)を右に見て三伏峠に通じる道」に立ち至り、今まさに南アルプスの東西南北の十字路に立っている事に感激した。荻野氏は道なき道を行き、苦労の果て南アルプスを横断したが、私は今明白な道を迷いながら縦断している。己の小ささを感じるばかりである
付近にはお花畑がいたるところにある。林の中のお花畑ではマルバタケブキが今を盛りといっせいに咲き誇っている。ちょっと大ぶりの花なので、きれいを通り越して、ちょっと気味が悪い気もするほどである。小河内岳はとてものんびりして眺めがよく気持ちの良い小屋である。水場がないのとテント場がないのが残念である。
高山裏避難小屋は小さな昔ながらの小屋である。(大門沢小屋に似ている)塩見小屋からのレターを主人に手渡す。ちょっと口の悪そうな主人であるが、手紙を持ってきたお礼に、水をくれた。水場まではかなり急なので、この水を使ってもいいといって、汲み置きの水2.5リットルを貰う。トイレ前のテント場には、前小河内岳から一緒の人が既にテントを張っていた。彼は三伏峠から来て、明日はここにテントを置き悪沢岳、赤石岳を登ってくるそうである。
かなりテントが濡れた状態なので乾かそうとするが、風もないので、なかなか乾かない。朝露がまたテントを濡らすので、乾く暇がないのである。
第5日 7月31日(水) 晴天
高山裏避難小屋 5:00
中岳 9:30
悪沢岳 11:25
荒川小屋 14:30
中岳に登り、荒川小屋への分岐に荷を置き、空身で悪沢岳(東岳)を往復する。途中の中岳避難小屋でミカンの缶詰を購入。水と一緒のビニール手提げに入れて山頂まで持ち上げる。山頂で食べたミカンの缶詰は最高で、このあと小屋でミカンの缶詰を買うのが習慣となるが、扱わない小屋も結構あって残念。悪沢岳はイワキキョウ、チシマキキョウなどキキョウの花が多いところで、中にチシマキキョウの八重咲きがあり、珍しいものと写真をとる。空身で登っているので気持ちも軽くなる。コースタイムより早かったのは後にも先にもここだけであった。
荒川小屋は森の中ではあるが、同じ森の中でも、熊の平、高山裏とは比較にならないほど明るく開けたテント場で気持ちが良い。特に主人の案内でお勧めのテント場NO.1を教えてもらった。木に囲まれた小さなテント専用サイトでとてもよかった。水場も近く、豊富で気持ちが良い。最高のテントサイトであった。できるだけテントを乾かすこと、食料を減らすことを心がけるが、朝方雨が降りまた濡れた。食事もあまり進まず、荷も軽くならないが、目に見えてザックの嵩が減っていくのはうれしい。ここまでくると、疲れもたまってくるが、残りの行程を考えると精神的に楽になる。
第6日 8月1日(木) 曇り
荒川小屋 5:20
赤石岳 8:20
百饟洞山の家 14:20
赤石岳までキツイ登りが続くが、下って百饟平は気持ちの良い高原だ。今日はガスがかかり、風があるので、ひやりとして気持ちが良い。水もあまり飲まない。途中で赤石岳の写真をとるべくガスが晴れるのを待ち続けるが、なかなかうまくいかない。あきらめて、百饟洞山の家に急ぐ。
部屋番号A1。3番目に到着の客となる。小屋の脇に沢があり、水に困らない。8人部屋に4人、比較的空いているようだ。聖岳の展望台があるが、ガスがかかり今日はあまりいい所は見せてもらえない。隣の客は広島から車に寝とまりしながら来た30代の岸さん。マッチョな体で荒川3山、赤石岳、聖岳を縦走中。私のテントスタイルに驚く。
東海フォレストのバスに乗るため、本日は今ツアー最初で最後の2食付の小屋泊まりとなる。夕食はとんかつ。蕎麦椀と生キャベツの千切りがたっぷり。久しぶりのご馳走にいつもより食が進み、たっぷり食べる。
第7日 8月2日(金) 晴天
百饟洞山の家 5:00
聖岳 11:05
聖平小屋 14:20
聖岳は森林限界が約2800mほど。さすが南アルプス最南の3000m峰だ。ダケカンバ、ハイマツなどが生えている。荒川小屋あたりから浦和から来た若い女性とほぼ同行している。彼女は松本のユースホステルのペアレントと二人連れである。かなり足が速く、連れのおじさんとこちらがほとんど一緒という状態。なかなか若くて頼もしい。百饟洞で同宿の岸さんが10分位後方を歩いていたところ、下りでつかまった木が抜け転落する事故にあった。幸い3メートルほど落ちたが、谷に落ちることなく道にとどまり打撲ですんで、九死に一生を得た。聖小屋に到着後最後のテントを張ると同時に、雨が降ってくる。遠くでゴロゴロと雷が鳴っている。ラジオをつけると「塩見岳で近畿ツーリストの団体が雷に打たれ、1人即死、5人が重傷。現在パーティーは自力で下山中」との報道を聞く。塩見岳の山容を思い出し、驚く。すぐに雨も上がり、のんびりテント前で食事。今回の目的である南アルプス3000メートル峰完登(農取岳、西農取岳は昨年登る)を終え、ほっとして良い気分だ。食材も粗方食べ尽くして楽しい。後は椹島に下るだけだと思うとなお楽しい。
第8日 8月3日(土) 晴天
聖平小屋 5:00
椹島 10:20
蒸し暑い林の中を軽快に歩く。彼方此方から湧水が流れてきており、水入らずの道である。
椹島発11:00のバスに間に合うようにとばす。かなり荷が軽くなっているのでコースタイムを短縮している。聖沢登山口から椹島まで約40分、炎天下のアスファルト混じりの舗装道路を歩かされる。これがきつい。椹島で初めて静岡鉄道バスが運休中との情報を得る。なんでもこの間の二つの台風の影響で道が壊れており、8月5日から再開の予定とのこと。タクシーしかないとの話で、相棒を探す。幸いにも、日立大田市のおばさん方お二人と同乗することになり、第一畑薙ダムバス停で1時間ほど待って静岡までのタクシーに乗る。料金は小型で21000円。ひとり7000円。バスの倍まではいかない料金でホッとする。
55歳の記念としてこの南アルプス縦走山行を計画したが、徐々に山から離れて街中に入る静岡駅までの車中で、計画通り無事完歩することができたことを皆に感謝しつつ、心地よい満足感に浸った。
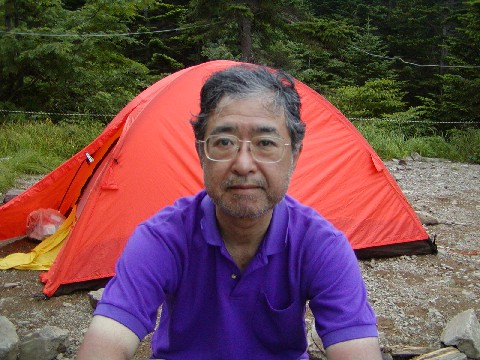
最後の宿泊地聖平にて。髭面で肩が落ちてます。ほんとに疲れました。
|
![]()
